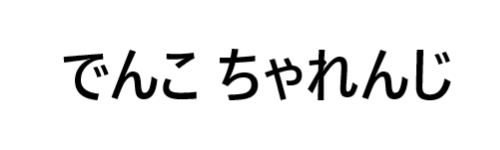問2.直径2.6[mm]、長さ20[m]の銅導線と抵抗値が最も近い同材質の銅導線は。
イ.直径1.6[mm]、長さ40[m]
ロ.断面積8[mm2]、長さ20[m]
ハ.直径3.2[mm]、長さ10[m]
ニ.断面積5.5[mm2]、長さ20[m]
はい、これはもう、ひたすら「計算」しました。
問題文のは、\( \dfrac{4ρL}{πD^2} \)を使って、\( \dfrac{4×ρ×20}{3.14×2.6^2} \)
分母、下は2.6×2.6=6.76、6.76×3.14=21.2264。分子、上は4×20で80、ρは皆にあるから無しとして、80÷だいたい21で、だいたい「3.8」。
イ.は問題文と同じ公式、\( \dfrac{4ρL}{πD^2} \)を使って、\( \dfrac{4×ρ×40}{3.14×1.6^2} \)
分母、下は1.6×1.6=2.56、2.56×3.14=8.0384。分子、上は4×40で160、ρ無しで160÷だいたい8で、だいたい「20」。(160÷8は暗算できたぞ!他はもちろん筆算。暗算、超苦手)
ロ.これも最初、\( \dfrac{4ρL}{πD^2} \)でいけるかなとやってみました。\( \dfrac{4×ρ×20}{8} \)。下、分母は結局断面積でしょ、というアサハカな考えで。ニ.までやったところで、近いのがない???と答えを見て再検討。問1.まで戻って改めて、この「4」は何だ?、Dは直径なのになぜ2乗なんだ?と、結局、問1.で”云々”で誤魔化した理屈を考えるはめになった結果。
下、分母は断面積、という考えは正しいっぽい。ただ、断面積を出した時のこの「4」はいらんっぽい。となると結局\( R= ρ \times \dfrac{l}{A} \)になるねえ。
で、数字入れてみた。\( R= ρ \times \dfrac{20}{8} \)。ρ無しで、20÷8で「2.5」。
ハ.これは、問題文やイ.と同じだーということで、\( \dfrac{4×ρ×10}{3.14×3.2^2} \)
分母、下は3.2×3.2=10.24、10.24×3.14=32.1536。分子、上は4×10で40、ρ無しで40÷だいたい32で、だいたい「1.2」。
ニ.これも1回はアサハカ計算やったんですが、改めまして\( R= ρ \times \dfrac{20}{5.5} \)。ρ無しで、20÷5.5で「3.6」。
答えは「ニ.」でした。